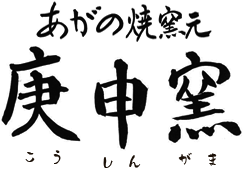薪で窯焚き[窯詰め編]
2014.10.02
残暑もかげりをみせはじめてすっかり秋っぽくなって参りました。
上野の里で秋といえば “スイーツ!” も もちろんいいんですが、それとは別で「上野焼 秋の窯開き」が開催されるのです。
その窯を“開く”ためにはまず“詰める”必要がある訳で、その様子をお届けいたしますは庚申窯3代目(仮)コウヅルユウタです。
庚申窯にある薪窯は普段メインで使用している電気窯の6倍近いスペースがあるので入れるやきものの数も5〜6倍ほどになります。
薪窯では思った通りの色がでないので(そこが薪で焼くことの醍醐味で、陶芸は「焼き一生」と言われたりします。)注文の品やオーダーメイドのものは普段 電気か灯油の窯で焼きます。
昨年は注文の品を作ることが多く、なかなか薪窯いっぱいになるほどの量のうつわが作れなかったので 薪での焼成は断念したのですが、今年はどうにかやれるので(といってもほんとは7月にやる予定だったのが間に合わなかったんですけど)僕としては庚申窯に戻ってきてからはじめての薪での窯焚きになります。
これが窯焚きのための薪。薪窯での焼成が少ないのも薪を集めるためのコストが電気などに比べてかかりすぎるということもあります。
一昔前では木造家屋の建て替えなどで壊した材木をもらったりできたそうですが 今では木造家屋自体減ってしまってそういう入手も難しくなっています。建築の材木は釘が打たれていて、釘の鉄分がいい感じにやきものの色合いを変化させたりするそうです。上の写真の赤い釉薬のものが“鉄”薬になります。
さてその薪窯の内部。
立てるほど高さはありませんが大人3人くらいは軽く入る広さです。
まずは掃除。
窯詰め作業がスタート。
窯の内部でも温度差がありまして基本的には下の方が温度が低く、上の方が高くなります。
そしてさらに空気の対流がいいとこの方が温度が上がり悪いとこは下がります。
そうすると一番奥の一番下の棚板、もしくは一番手前の一番下が一番温度が低くなることになります。
逆に一番温度が高いのは真ん中付近の一番上となります。
また釉薬もその原料によって溶ける温度(融点)が違いまして
例えば赤い薬の“鉄”は低い温度でも溶けるので あまり上の方に置くとうつわから棚板まで釉薬が流れ着いてキズモノになってしまったり、グレーの“ワラ灰”の薬は比較的高い温度で溶け出すので下の方だと薬が溶けなくて全然色が出ないなんてことになります。
そういったことを加味して窯に詰めていく作業は頭脳プレイでもあり、うつわ同士がくっつかないように薬がはげないように並べるのは神経戦でもあります。しかも薪窯は中に入って中腰でその作業をやらなきゃいけないから腰にくる!ってことで大変なのです。
ではわたくしの方はカメ子に徹していたのかと言いますとそういう訳でもなく、たとえば貝に粘土を詰めたりしていました。
これは何かと言いますと “貝高台”といいまして古くからある技法でうつわから釉薬が流れてしまった際にうつわと棚板との熔着を防ぐためのものです。そうすることで貝殻で空いた隙間から薪の焼成ガスが高台内にも当たって土を焼き締めたり、高台の接着部分に貝殻の形紋が残ったりして見た目的にもかっこよくなっちゃうのです。
ちなみに上の写真のおちょこが置かれているのは薪をくべる炉から炎が出てくる縁の部分でして、「火あたり」と言われたりします。
直接あたるため変化が予測できないのですがその分予想外の色が出たりするそうです。
上には空気穴があってこれを開閉したりで焼き具合を調整します。
窯の内部のレンガは長年の使用でもはや溶けて融着しています。さわってもやきものみたいにテカテカつるつる。
その他には棚板やこれもやきものから釉薬が流れ着いたときに棚板にダメージを残さないための(またはほかのやきものにまで被害を広げないための)陶板に“アルミナ”を塗ったりしていました。
アルミナというのは“白い魔法の粉”でございまして、アルミの原料のボーキサイトを加工して作られるものらしいんですがこれが融点が高くて強靭でとにかく硬い!ということで先ほどの貝同様1200℃程度ではびくともしません。
これを棚足や棚板との間、または先ほどの貝高台の貝に塗り付けておくことで「非接着剤」の役目を果たします。
現代の陶芸には欠かせないアイテムです。
こんな感じで奥から積み上げていって上まで積んだら手前にまた積んでと繰り返します。
この写真で奥の1列が完成。
それを3列繰り返して下の写真のように。
ここまでの窯詰めの作業だけで2日かかりました。
しかし次こそが本番なのです。
[窯焚き編]につづく